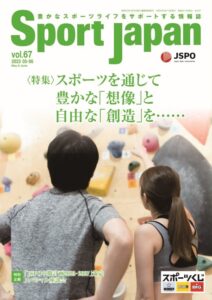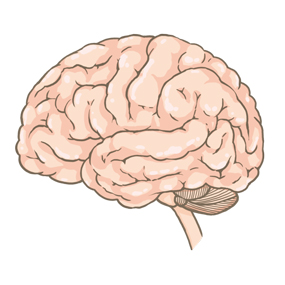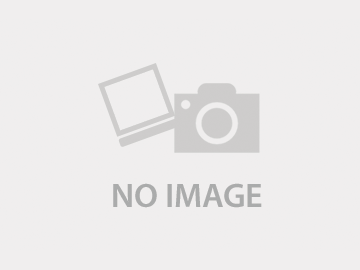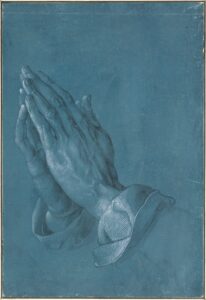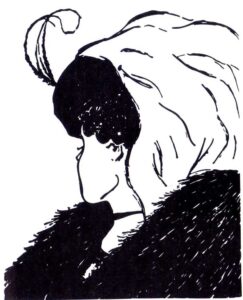目次
はじめに
飲み会で上司が「昔はよかった」という話を始めた。みんな適当にうなずいて「そうですねー」と笑う。でも新入社員だけは真顔のままだ。その瞬間、場の空気が微妙に重くなる。
私たちは面白いから笑うと思いがちだが、実際はそう単純ではない。多くの場合、「ここで笑うべきだ」と察するから笑っている。では、その「べき」は誰が決めているのだろう。なぜ笑わない人がいると居心地が悪くなるのだろう。
笑いは確かに場を和ませる潤滑油だが、同時に人と人との境界線を引く道具でもある。誰の笑いが誰を仲間に入れ、誰を排除するのか。その仕組みを理解すれば、職場や人間関係の見えない力学が見えてくるはずだ。
日常会話の中の笑い
実は、人はジョークがなくても笑っている。雑談に混じる笑いの80%は、面白さとは関係なく、単なる相槌や文末の句読点のような役割を果たしているという研究がある。例えば「資料できました」と言いながら軽く笑うと、「大した問題じゃないですよ」「気軽に話しかけていいですよ」というメッセージになる。手話でも同じで、文末に肩を揺らす笑いが入ると会話がスムーズに次の話題に移る。つまり笑いは意味を伝えるより、会話のリズムを整える役割が大きいのだ。
しかし、このタイミングが少しでもずれると、笑いは逆効果になる。早すぎる笑いは嘲笑に聞こえ、遅すぎる笑いは白々しく感じられる。だから私たちは無意識に場の空気を読んで、表情筋を微調整している。興味深いことに、会話分析の研究では、話している人より聞いている人の方がよく笑うことが分かっている。聞き手は笑いで相手の話を肯定し、自分が協力的だと示している。逆に笑いを返さないことは、やわらかな拒否のサインでもある。
この計算は無意識に行われるため、発達障害のある人が「笑いどころ」をつかみにくいのは、この隠れた計算が働きにくいためだと考えられている。研究者のスコットは、人間の笑いには音楽の「合奏」のような性質があると指摘する。笑いの周波数やタイミングが合えば安心感が広がり、外れれば緊張が走る。電話では顔が見えない不安を埋めるため、うなずきの代わりに「ハハッ」が増える。メールやLINEでは絵文字に置き換わり、笑いが視覚記号に変わる。媒体は変わっても、私たちは何らかの方法で「ここは敵がいる場所じゃない」と伝え続けているのだ。
この日常的な笑いの交換は一見平等に見えるが、実際には性別によって大きな偏りがある。

笑いに潜むジェンダーの役割
笑いには明確な男女差がある。街頭で人々の会話を観察した研究によると、男女のペアでは笑うのが女性、笑わせるのが男性という傾向が強いことが分かった。「ウケ狙いの男性と愛想笑いの女性」という構図は、今でも多くの職場に残っている。会議で上司がジョークを言うと、女性社員が真っ先に笑って場を和ませる。この現象は単なる性格の違いではない。笑う側と笑わせる側の役割分担は、誰の発言により重みがあるかを示しているからだ。
ただし、環境が変わると力学も変わる。女性同士の雑談では笑いの発生率が最も高く、序列を気にせずに声が重なり合う。インターネットでは女性コメディアンが急増し、「笑わせる側」に回る例も増えてきた。しかし根深いバイアスは残っている。実験では、同じジョークでも語り手が女性だと「攻撃的」と評価されやすいことが示されている。笑いはジェンダー観を映す鏡であり、同時にその偏見を打ち破る道具にもなり得るのだ。
生理学的な研究では、女性の方が表情筋の反応が早く、短い間隔で笑いを返すことが分かっている。ただし、これが社会的な学習によるものか、生来の感受性の違いかは決着していない。職場での「笑い疲れ」という訴えは、主に愛想笑いを担う側から出る。心から笑えないのに笑い続けるギャップは、交感神経を緊張状態に保ち、仕事以上に体力を奪う。研究者が愛想笑い時の皮膚電気反応を測ったところ、ストレスホルモンの上昇が確認された。笑いは時として、甘い装いで忍び込む見えない労働でもあるのだ。
このように笑いは、性別役割を通じて人間関係の力学を作り出している。しかし、これは職場の序列や文化的背景とも密接に関わっている。

権力と文化が作る笑いのルール
笑いは社会の剣にも盾にもなる。上下関係がはっきりした場では、上位者の笑いが起爆装置となり、下位者は条件反射のように笑う。逆は危険だ。下位者が先に笑えば無礼とみなされることがある。笑えと命じられるわけではないのに、表情筋は権力の匂いを嗅ぎ取る。一方で、笑いは抵抗の武器にもなる。中世の宮廷道化師は王を笑い者にして諫言し、現代の風刺番組は権威に挑戦する。みんなで同時に笑うことで恐れが薄れ、批判の力が集まる。ある研究者はこれを「嘲笑による規範監視」と呼んだ。集団は笑いで規則破りを罰するが、同じ笑いが支配者をも刺す刃になる。
文化による違いも無視できない。アメリカでは「ユーモアがある=社交上手」だが、日本や中国では「真面目が美徳」という価値観が根強い。調査では、自分を「ユーモアのある人」と答える日本人の割合はアメリカ人の半分以下だった。こうした違いは国際的なチームで摩擦を生む。欧米人のジョークが東アジアで滑るのは、語学力の問題だけではない。笑いを肯定する規範そのものが違うからだ。お互いの「笑いのルール」を知らずにジョークを言うと、親しみやすさを示すつもりが場を凍らせてしまう。だから多国籍チームでは、まず笑いの文化的翻訳から始める必要がある。
このように笑いは、権力や文化という大きな枠組みに影響されながら、私たちの日常の人間関係を形作っている。
まとめ
飲み会での上司の昔話に、みんなが笑ってその新入社員だけが真顔だったあの瞬間を思い出してみよう。あの時何が起きていたのかが、今なら少し見えてくる。笑いは確かに場を和ませる効果がある。しかし同時に、誰が内側で誰が外側かを示す境界線を引く道具でもある。愛想笑いを強要する見えない圧力、ジェンダー役割による笑いの偏り、権力関係が作り出す笑いの序列。
次に笑いの場面に遭遇したとき、私たちはどちらの作用を選ぶのだろう。疲れている人にもう一つの愛想笑いを求めるのか、それとも誰かの居場所を笑いで奪うのか。「笑い上手」とは、面白い話をたくさん知っている人のことではないのかもしれない。笑いが持つ複雑な力を理解し、それをどう使うかを選べる人のことなのだろう。あの新入社員が感じていた居心地の悪さは、確かに理解できる。だが、そんな「みんなが笑わなければならない空気」という状況そのものを笑い飛ばせる諧謔精神を持ちたいものである。
参考文献
Billig, M. (2005). Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour. London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781446211779
Jiang, T., Li, H., & Hou, Y. (2019). Cultural differences in humor perception, usage, and implications. Frontiers in Psychology, 10, 123. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00123
Provine, R. R. (1993). Laughter punctuates speech: Linguistic, social and gender contexts of laughter. Ethology, 95(4), 291–298. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1993.tb00478.x
Scott, S., Lavan, N., Chen, S., & McGettigan, C. (2014). The social life of laughter. Trends in Cognitive Sciences, 18(12), 618–620. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.09.002