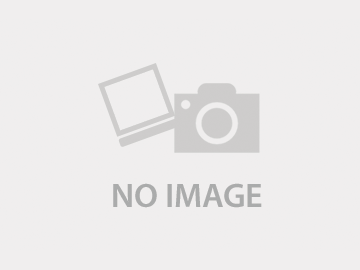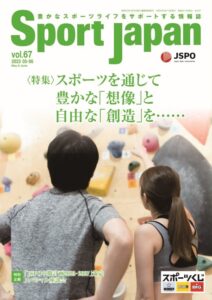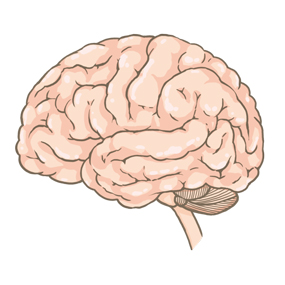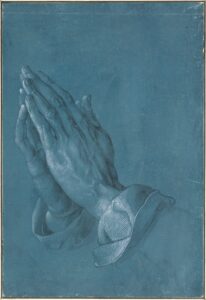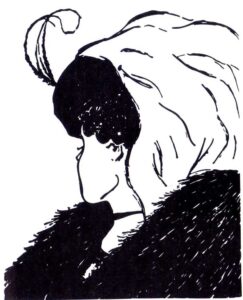目次
はじめに
昔のバラエティ番組を見返していると、今では笑えない場面に出くわすことがある。体型や容姿をネタにして笑いを取る芸人、失敗を延々とからかう演出。当時は爆笑していたのに、今見ると「これはちょっと...」と眉をひそめてしまう。
なぜ同じ映像なのに、昔は面白くて今は面白くないのだろう。笑いとは一体何なのか。何が面白くて、何がそうでないのか。同じ出来事でも、時代や人によって反応が全く変わる。その違いはどこから生まれるのだろうか。
昔から多くの学者が笑いの謎を解こうとしてきた。最新の脳科学も加わって、「面白さ」の正体が少しずつ見えてきている。普段何気なく笑っている私たちの頭の中で、実は驚くほど複雑な判断が瞬時に行われていることが分かってくるはずだ。
昔の学者たちが考えた三つの説
笑いについて考えた昔の学者たちは、大きく分けて三つの説を考え出した。
一つ目は「相手より上に立った時に笑う」説だ。プラトンやホッブズという哲学者が言った考えで、上司が階段で転ぶのを見て思わず笑ってしまうのがこの例だ。「あ、自分の方がうまくやれてる」と感じるから笑うのである。
でも、この説だけでは説明できない笑いもある。早口言葉で舌が回らなくなったり、言葉遊びで変な音ができたりした時、別に誰かを馬鹿にしているわけじゃないのに笑ってしまう。二つ目は「たまったストレスが一気に出る時に笑う」説だ。フロイトなどが考えた説で、緊張する面接が終わった途端に笑い出すのがまさにこれ。ため込んでいた緊張が一気に解放されるから笑うのである。
ただし、この説にも問題がある。のんびりした休日にコメディ番組を見て大笑いすることがあるが、そのときは別にストレスがたまっているわけじゃない。それでも面白いものは面白い。三つ目は「予想と違うことが起きた時に笑う」説だ。カントやショーペンハウアーという哲学者が考えた説で、ジョークのオチや、猫が犬みたいに鳴く動画など、確かに「あれ?」と思った瞬間に笑いは生まれる。
しかし、予想外の出来事がすべて笑いになるわけではない。事故や災害のニュースは、どんなに予想外でも人を笑わせない。むしろ凍りつかせる。単に「違った」だけでは笑いは生まれないのだ。
この三つの説は、それぞれ笑いの一部分を説明するが、完璧ではない。そして現代になって、もっと新しい考え方が登場した。
新しい発見「良性違反理論」
最近になって、アメリカの研究者マグロウとウォレンが「良性違反理論(Benign Violation Theory)」という新しい説を発表した。名前は難しいが、簡単に言うと「ちょっと悪いことだけど、実害はない時に笑いが生まれる」という考え方だ。
例えば、お葬式でピエロが突然現れて棺を蹴飛ばす映像があったとする。普通なら「ひどい!」と思うだろう。でも、実は棺は空っぽで、亡くなった人が生前に「最後は派手にやってくれ」と頼んでいたと分かると、急に笑えるようになる。同じ「ルール破り」でも、状況次第で「まあいいか」に変わるのだ。
逆に、災害の被害者をからかうようなジョークは、被害が現実的すぎて「害がない」とは思えず、嫌な気分になる。SNSで炎上するジョークの多くは、この「害があるかないか」の判断が人によって違うから起こる。大事なのは「心の距離」だ。遠い国の政治家がパイに顔を突っ込まされる映像は笑えても、自分の身近な上司が同じ目に遭うのは笑えない。距離が遠いほど「まあ大丈夫だろう」と思えるようになる。
さらに面白いのは、「笑っちゃダメ」な場面ほど笑いが大きくなることだ。図書館の静寂、試験中の緊張、お葬式の厳粛さ。ルールが厳しいほど、ちょっとしたことでも大爆笑になる。まるで圧力鍋の蒸気のように、制限が強いほど笑いが勢いよく噴き出すのだ。
脳の中で起きている高速判定
笑いは単なる感情のように見えるが、実は脳がものすごく速く複雑な計算をした結果だ。ジョークを聞いた時、私たちの脳では1秒もかからずに何段階もの判断が行われている。
まず側頭葉(言語理解を担当する部位)が言葉の意味を理解する。次に前頭前野(高度な判断を行う脳の司令塔)が「これはルール違反かな?」「でも害はないかな?」を瞬時にチェックする。そして腹側線条体(快感を生み出す部位)がドーパミンを放出して「面白い!」という感覚を作り出し、最後に運動皮質が顔の筋肉を動かして笑顔を作る。認知・倫理・快感・運動の四つの段階が、ロケットの点火のように連続して起こるのだ。

この高速で柔軟な判断こそが、人間らしさの核心かもしれない。最新のAIは駄洒落を作ることはできても、「この場面でこのジョークを言っても大丈夫か」を判断するのは苦手だ。逆に、前頭側頭型認知症の患者は皮肉を真に受けてしまったり、笑うタイミングがずれたりする。適切な判断ができなくなると、笑いも壊れてしまうのだ。
面白いことに、よく笑う人ほど創造性が高いという研究もある。違う考えを安全に組み合わせられる人ほど、新しいアイデアを思いつくのが得意らしい。脳の「面白がる回路」と「ひらめく回路」は、同じところを使っているようだ。
文化の違いも大きい。日本人がよくする「苦笑い」は、自分を下げて場を和ませる技術だが、外国では「嫌がっている」と思われることがある。同じ笑顔でも、国によって「OK」のルールが違うからだ。こうして見ると、笑いは思っている以上に頭を使う行為だということが分かる。
笑いが社会を作っている
昔のバラエティ番組で体型をからかうギャグを見て笑っていた私たちは、実はすごく複雑な判断を瞬時に行っていた。当時は「ちょっとした悪ふざけで害はない」と感じていたが、今では「これは人を傷つける」と判断が変わったのだ。
笑いとは、単純な反応ではない。いろんな要素が絡み合って、さらに「害があるかないか」という高度な判断が加わった、人間ならではの複雑な反応なのである。私たちは毎日のように「ちょっと変なこと」に出会い、そのたびに無意識に「これは笑っていい場面か」を判断している。その小さな判断の積み重ねが、実は「何が面白くて何がダメか」という社会全体のルールを作り上げているのだ。
とはいえ、あまりに窮屈な社会も笑えたものではない。
人間の本質は愚かさに宿る。
「みんな違ってみんなダメ」のマインドで、ヒトとして生きることの哀しさを笑い飛ばして生きていきたい。
参考文献
Billig, M. (2005). Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour. London: Sage Publications. https://doi.org/10.4135/9781446211779
Jiang, T., Li, H., & Hou, Y. (2019). Cultural differences in humor perception, usage, and implications. Frontiers in Psychology, 10, 123. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00123
Provine, R. R. (1993). Laughter punctuates speech: Linguistic, social and gender contexts of laughter. Ethology, 95(4), 291–298. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1993.tb00478.x
Scott, S., Lavan, N., Chen, S., & McGettigan, C. (2014). The social life of laughter. Trends in Cognitive Sciences, 18(12), 618–620. https://doi.org/10.1016/j.tics.2014.09.002