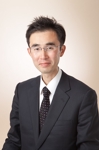目次
はじめに
日曜の動物園でのことだ。チンパンジーの子どもがほうきを奪って逃げる。追いかける飼育員、響く「ククク…」という低い息づかい。ガラスのこちら側で吹き出した私たちと、向こうで揺れる黒い肩。進化の歳月は、この笑い声を分け隔てたのか、それとも繋いだのか。
仕事帰りに動画サイトを開けば、人間も同じように笑いに転げ回る。「たかが笑い」と片づけるには、あまりにしつこく文明に張り付いている。狩猟採集の焚き火からVR空間まで、場が変わっても笑いだけは抜け落ちない。
なぜなのだろう。笑いは生存に不要な贅肉なのか、むしろ集団を守る筋肉なのか。この記事では、霊長類の遊び声を手がかりに、「笑いはどこで生まれ、何を守ってきたのか」を探っていく。まずは彼らの「遊び笑い」を観察し、続いて私たちの社会での役割を考え、二種類の笑いを見分け、そして静かに振り返る。途中で笑ってもらえたら、それもまた証拠になるだろう。
霊長類の遊び笑い
まずは動物園のフェンスを越え、森へ入ってみよう。チンパンジーの幼獣は取っ組み合いの最中、呼気と吸気を交互に使うリズムで「パンティング」と呼ばれる声をあげる。ゴリラやボノボでも似た音が記録されており、ヒトの「ハハハ」と連続する吐息とは形式が違うが、感情の立ち上がりは不思議と共通している。
2010年、ダーウィラ=ロスらは五種の大型類人猿をくすぐり、声紋を比較した。解析結果は系統樹の形で並び、笑い声の特徴が進化史を忠実になぞることを示した。つまり、私たちの笑いは祖先の遊び声を直接のルーツとしているのだ。
興味深いのは、遊び笑いが必ず安全な環境で起こることだ。肉食獣の気配がすれば子どもたちは黙り、戯れを中断する。笑いは「今は戦闘モードではない」という旗印であり、仲間同士の信頼を再確認するサインでもある。
霊長類の社会は順位闘争が厳しい。しかし遊びの時間だけは支配者も下位個体もルールを外し、奪ったほうきで追いかけたり追われたりする。その最中に漏れるパンティングは、階級を一時停止させる「休戦の合図」として機能しているのかもしれない。
この合図はヒトにも残っている。子どもの鬼ごっこでは「待って待って」と笑い声が枕詞のように飛び交い、転倒してもすぐに立ち上がる。大人になってもスポーツやボードゲームで、劣勢側が笑いながら降参のポーズを取る光景は珍しくない。遊び笑いは闘争を模倣しながら、実際の危害を最小化する安全装置として作用している。
社会的接着剤としての笑い
ヒトは一人でいるときよりも、誰かと一緒のとき三十倍多く笑うという調査がある。面白い話がなくても、視線が合えば口元が緩む。笑いは情報ではなく「関係」そのものを運ぶ媒体らしい。
進化人類学者ロビン・ダンバーは、霊長類の毛づくろいが担ってきた結束機能を、ヒトは笑いで代替したと論じた。頭を一対一でつつく代わりに、ジョークを放って集団全体を包み込む。笑い声は空気感染し、数十人規模でも同時に鎮痛ホルモンを放出させることができる。
実験でも、コメディ映像を見て大笑いした被験者は痛みに強くなる。この変化はエンドルフィン系の活性化で説明でき、同時に「仲間と同じ瞬間に笑った」という記憶が信頼感を底上げする。笑いは脳内の報酬と社会的記憶の二重の回路を束ねる接着剤なのだ。
ただし、この接着剤はときに排他的でもある。内部の結束が高まるほど、部外者は「笑いの文脈」を共有できず疎外感を味わう。閉じた輪の内側でだけ通じるあだ名や内輪ネタは、笑いが築いた見えない壁の証拠だ。笑いは温かい手ざわりの裏に、冷たい境界線も同時に描き出す。
それでも私たちは笑いを手放さない。会議室で煮詰まった空気を、誰かの軽口がほぐすことがある。深夜残業で疲労が極まった夜、ちょっとした言い間違いに皆が吹き出し、「まだ大丈夫だ」と安心する。笑いは集団の疲れを癒す薬のようなものだ。ひとつの笑いが伝染すると、一瞬で場の重苦しさが軽くなる。このとき笑いは、個人の感情を超えて集団全体を支える力として働いている。
しかし、よく観察してみると、その「軽口」にも違いがある。心の底から湧き上がる笑いと、場の空気に合わせて作る笑いは、同じ「笑い」でも質が異なる。この違いこそが、笑いの複雑さを物語っている。
二種類の笑い
鏡の前で練習する営業スマイルと、友達の失敗談を聞いて思わず出てしまう笑い。見た目は似ているが、実は全く別物だ。前者は「非デュシェンヌ笑い」、後者は目の周りの筋肉まで動く「デュシェンヌ笑い」と呼ばれている。頭で考えて作る笑いか、感情から自然に湧き出る笑いか。この違いは、人間の進化の歴史と深く関わっている。
チンパンジーたちのパンティングは明らかに後者のタイプだ。彼らは作り笑いをしない。人間はそれに加えて、意図的に笑う能力を身につけた。息づかいを器用に操って、相手に「敵意はありません」というサインを送れるようになったのだ。
ただし、この新しい能力には副作用もある。場の雰囲気に合わせて笑っているうちに、本心とのギャップがストレスになることがある。さらに、この笑いは相手を馬鹿にしたり見下したりする道具にもなる。相手の失敗を強調して、自分を優位に見せる。笑いは時として、人を傷つける刃物に変わってしまう。
一方で、本物のデュシェンヌ笑いは意識してマネするのが難しい。赤ちゃんがお母さんの顔を見てにっこりする瞬間、目尻のしわは偽物ではない。ここにこそ笑いの本質がある。実験では、本物の笑いを交わした人同士は、その後のゲームで相手を裏切る確率が大幅に下がったという。私たちは表情筋の微妙な動きで、将来の信頼関係を築いているのだ。
結局、「笑い上手」な人とは、この二種類の笑いを使い分けられる人のことかもしれない。素直な気持ちを表しつつ、場の空気も読める。その技術は、言葉よりもずっと古くから人間が身につけてきたコミュニケーション能力なのだ。
まとめ
動物園のフェンスを思い出してみよう。あの日のパンティングと私たちの笑い声は、同じ周波数で空気を揺らしていたのかもしれない。もしそうなら、笑いは偶然の贈り物ではなく、祖先が磨き上げた「共に生き延びるための音」だ。
もっとも、笑いが万能薬というわけでもない。時には人を傷つけ、時には人を結びつける。そう考えると、大切なのは笑いそのものではなく、どう使うかなのだろう。
動物園のあの日を思い出してみる。チンパンジーたちがほうきで遊んでいるのを見て、私たちも自然と笑った。言葉も通じない相手なのに、なぜか楽しさが伝わってきた。もしかすると、笑いの本来の姿はそこにあるのかもしれない。相手が誰であろうと、その瞬間の楽しさを共有する。それが笑いの持つ最もシンプルで、最も大切な機能なのではないだろうか。
参考文献
Davila‑Ross, M., Owren, M. J., & Zimmermann, E. (2010). The evolution of laughter in great apes and humans. Communicative & Integrative Biology, 3(2), 191–194. https://doi.org/10.4161/cib.3.2.10944
Dunbar, R. I. M. (2022). Laughter and its role in the evolution of human social bonding. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 377(1863), 20210176. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0176
Gervais, M., & Wilson, D. S. (2005). The evolution and functions of laughter and humor: A synthetic approach. Quarterly Review of Biology, 80(4), 395–430. https://doi.org/10.1086/498281
Provine, R. R. (1993). Laughter punctuates speech: Linguistic, social and gender contexts of laughter. Ethology, 95(4), 291–298. https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.1993.tb00478.x