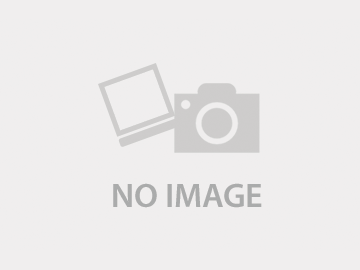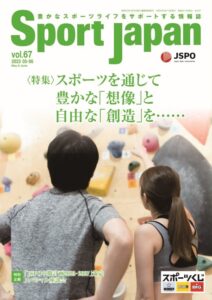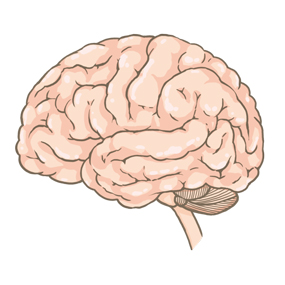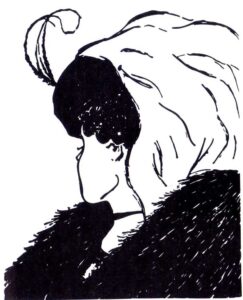目次
はじめに
「このろくでもないすばらしき世界」という言葉がある。この「世界」を「人間」や「教室」に置き換えても、しっくりくるのではないだろうか。
人間は、素晴らしさとろくでもなさを両方持って生きている。たとえば、仲間を守りたい気持ちが、誰かをハブる気持ちにつながることがある。どこかのグループに入りたい気持ちは、仲間外れにされたときの痛みと裏表の関係だ。
この記事では、教室や職場で起こる「いじめ」について、正義感、所属欲求、日常的サディズムといったキーワードを使って、そのメカニズムを探ってみたい。
正義の裏にある「いじめ」
「あいつはズルをしている」「みんなと違う」。こんな言葉から、いじめが始まることがある。
人間には「強い互恵性」という心の働きがある。これは、自分が損をしてでも仲間を助け、逆にルールを破る人には厳しく罰を与える性質のことだ。たとえば、掃除をサボる人がいたら、自分の時間を使ってでもその人を責める。これは一見、正義のように見える。
実は、私たちの脳は「公平であること」を「ごほうび」として感じるようにできている。実験では、公平に扱われたときに、お金をもらったときと同じような脳の部分が活動することが分かっている。さらに驚くことに、ズルをした人を罰するときにも、同じ「ごほうび」の感覚が生まれる。つまり、私たちは誰かを「正義の名のもとに」罰することに、快感を覚えてしまうのだ。
心理学者の研究によると、正義感には4つのタイプがある。自分が損をしたときに怒るタイプ、他人が不公平に扱われるのを見て怒るタイプ、自分だけ得をして申し訳なく思うタイプ、他人を傷つけて後悔するタイプだ。
このうち、自分が損をしたときに怒るタイプの人は、疑い深く、復讐心が強い傾向がある。ちょっとしたことでも「自分だけ損している」と感じやすく、それがいじめのきっかけになることもある。
仲間でいたい気持ちと、仲間はずれの痛み
人間には「所属欲求」という、誰かとつながっていたい気持ちがある。これは食欲や睡眠欲と同じくらい大切な欲求だ。
仲間はずれにされると、体の中で大きな変化が起こる。ストレスホルモンが増え、体の抵抗力が落ちる。頭の働きも悪くなる。これは大昔、群れから離れることが死を意味したことの名残りかもしれない。
ある実験では、コンピュータ上でキャッチボールをするゲームを使って、仲間はずれの体験をさせた。途中からボールが回ってこなくなると、参加者の脳では、他人の気持ちを考えたり、自分の感情を整理したりする部分が強く反応した。
仲間はずれの痛みは、体の痛みと似た反応を脳に起こす。だから、いじめられた記憶は深く心に刻まれる。一方で、誰かを仲間はずれにすることで、残ったメンバーの結束が強まることもある。「あいつは違う」と誰かを排除することで、「私たちは同じ」という安心感が生まれる。これも、いじめがなくならない理由の一つだ。
人の痛みが"楽しい"と感じてしまうとき
サディズムと聞くと、特別な人だけの話だと思うかもしれない。でも実は、私たちの多くが「日常的サディズム」という傾向を持っている。
心理学者によると、この傾向は動物の狩りの本能から来ているという。獲物を追いかけ、捕まえるとき、動物は興奮する。この感覚が人間にも残っていて、他人の困った顔や苦しむ姿を見ることに、ある種の興奮を覚えてしまうのだ。
実際の調査では、「人をからかって困らせるのが面白い」「ケンカを見ると興奮する」という質問に、多くの人が「少しそう思う」と答えている。これは特別なことではなく、程度の差はあれ、誰もが持っている傾向なのだ。
脳の研究では、サディスティックな人は他人の痛みに敏感に反応することが分かっている。つまり、相手の苦しみをよく感じ取り、それを「楽しむ」のだ。また、誰かが苦しむ映像を見ると、攻撃性に関わるホルモンが増えることも分かっている。
日常的サディズムが強い人ほど、いじめの加害経験が多く、ネットでの悪口も多い。特に退屈なときに、この傾向が強まる。刺激がほしくて、誰かをいじめて楽しもうとしてしまうのだ。
おわりに
こうして見ると、私たちの本能はいじめを起こしやすい仕組みになっている。
自分と違うタイプの人がいれば排除したくなる。ルールを守らない人がいれば懲らしめたくなる。しかも、いじめることが楽しくて、やめられなくなる危険性まである。
では、どうすればいいのか。正直なところ、はっきりとした答えはない。
生きていく上で誰かを傷つけることは避けられない。だからこそ、自分が行う悪を自覚し、その居心地の悪さから目を背けないことが大切だ。
誰かを傷つけなければならないとき、ためらいながら、相手の痛みを想像する。その重さを感じ続けることが、私たちにできる最低限の倫理なのかもしれない。
参考文献
Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2017). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Interpersonal development, 57-89.
Buckels, E. E. (2018). The psychology of everyday sadism (Doctoral dissertation, University of British Columbia). https://dx.doi.org/10.14288/1.0369056
Corradi-Dell'Acqua, C., Civai, C., Rumiati, R. I., & Fink, G. R. (2013). Disentangling self- and fairness-related neural mechanisms involved in the ultimatum game: an fMRI study. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 8(4), 424-431.
Fehr, E., Fischbacher, U., & Gächter, S. (2002). Strong reciprocity, human cooperation, and the enforcement of social norms. Human Nature, 13, 1-25.
Foulkes, L. (2019). Sadism: Review of an elusive construct. Personality and Individual Differences, 151, Article 109500. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.07.010
Groskurth, K., Nießen, D., Rammstedt, B., & Lechner, C. M. (2023). The imperfect altruist: Inequity aversion and prosocial behavior. Personality and Individual Differences, 208, Article 112187.
Mwilambwe-Tshilobo, L., & Spreng, R. N. (2021). Social exclusion reliably engages the default network: A meta-analysis of Cyberball. NeuroImage, 227, 117666.
Nell, V. (2006). Cruelty's rewards: The gratifications of perpetrators and spectators. Behavioral and Brain Sciences, 29(3), 211-257. https://doi.org/10.1017/S0140525X06009058
Pfattheicher, S., Lazarević, L. B., Westgate, E. C., & Schindler, S. (2021). On the relation of boredom and sadistic aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 121(3), 573-600. https://doi.org/10.1037/pspi0000335
Plouffe, R. A., Saklofske, D. H., & Smith, M. M. (2017). The Assessment of Sadistic Personality: Preliminary psychometric evidence for a new measure. Personality and Individual Differences, 104, 166-171. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.07.043
Schmitt, M., Baumert, A., Gollwitzer, M., & Maes, J. (2010). The Justice Sensitivity Inventory: Factorial validity, location in the personality facet space, demographic pattern, and normative data. Social Justice Research, 23, 211-238.
Tabibnia, G., Satpute, A. B., & Lieberman, M. D. (2008). The sunny side of fairness: Preference for fairness activates reward circuitry (and disregarding unfairness activates self-control circuitry). Psychological Science, 19(4), 339-347.