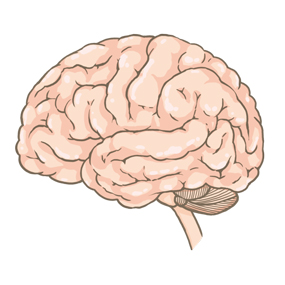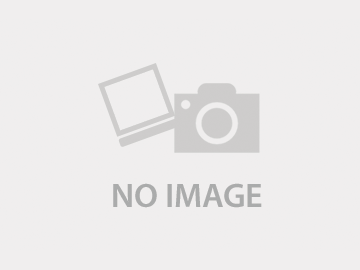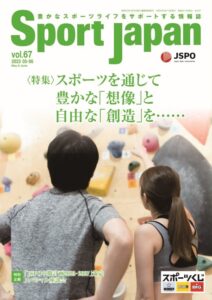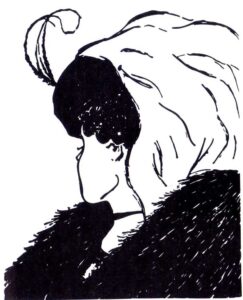私は、書いたそばから自分の文章の内容を忘れてしまうという特技がある。
つい先日、お世話になっている素材メーカーの方とランチをご一緒したとき、
「佐藤先生って推しはありますか?」
と聞かれた。
私は「推し」を持っていない。ただ、「推し」について文章を書いた記憶だけはある。内容はぼんやりしている。
そこで昔の記事を検索してみたところ、ようやく思い出した。推しとは、広い意味で「愛着」の問題として捉えられる。
人は気づかないうちに、何かしら愛着の対象を持っている。
スヌーピーのチャーリー・ブラウンが手放さないタオルケットのようなものや、自宅のペット、恋人、家族、あるいは会社そのものかもしれない。
こうした対象は身近にありすぎて普段は重要性に気づかないが、離れてみて初めて大切さがわかる。出張先で子どもが恋しくなるとか、海外に行くと日本語や日本食が恋しくなるように。
愛着を支えている背景には、オピオイドホルモンの作用がある。愛着対象と一緒に過ごすとオピオイドが分泌され、心が落ち着き、温かい感情に包まれる。さらに、免疫系にも良い影響を与えるため、体の調子も整う。
逆に、愛着対象と離れるとオピオイドが不足し、心身のバランスを崩すことがある。無意識のうちに分泌されていたものが途切れ、心が不安定になり、免疫機能まで下がってしまう。ペットロスのようなものがこれに当たる。
さて、ここで「推し」に戻る。
「推し」とは、一種の“愛着ビジネス”なのではないか。社会のつながりが弱まり、身近な愛着対象を作りづらい人々は、慢性的なオピオイド不足に陥りやすい。
そこに“推せる対象”が差し出され、課金という形で愛着が結びつく。強化され、循環し、依存にも似た構造が生まれる。海外ではオピオイド依存が問題になっているが、日本では形を変えたオピオイド依存が「推し活」になっている、と考えることもできる。
だからといって、自然な愛着対象としてペットの飼育に補助金を出せばいいかというと、それはそれでどこかディストピア的で落ち着かない。
地元の過疎が進んだ地域のドラッグストアに行くと、都市部と比べてペットフードの棚が異様に長く、お酒の棚も人口比で見るとやたら長い。ディストピアというほどではないが、少し胸の奥がざらつく光景である。
結局、人は何かに推し、何かに寄りかかりながら生きているのかもしれない。推しも地元のスポーツチームや自慢の孫くらいで済めば健全なのかもしれないが、推しビジネスは、こうした自然な愛着を精製し、白砂糖のように依存性の高いものへ変えてしまっている気がする。
できれば、体に入れるものと同じように、推しも自然無添加のものを心がけたい。